*農場の紹介*

 農場のある場所は山形県内陸の北部、山をいくつか越えれば秋田県です。
農場のある場所は山形県内陸の北部、山をいくつか越えれば秋田県です。
盆地のため夏は暑く、冬は2mくらい雪が積もります。秋も10月になれば雨の日が多く、晴れでも昼頃まで深い霧に覆われることもしばしばです。なかなか農業をやるには厳しい自然条件です。 昼夜の温度差が大きいというのが、唯一良いところでしょうか。
こんな土地で有機農業をはじめて20年以上経ちます。周りには手本も無く、無理だという人ばかり。 いくつかの参考書を頼りに、右も左もわからない状態ではじめました。
なぜ一人でこんな事を始めたかといえば・・・・毒にまみれた仕事をするのが嫌になった。からでしょうか。
農業は自然相手の仕事ですが、通常は農薬や化学肥料で自然を都合のいいようにコントロールし、収穫を増やすことで成り立っている仕事です。 毎日何年も自然相手に仕事をしているうちに、農薬にまみれて仕事することに嫌気がさしたというか、もっと自然に寄り添った仕事がしたくなったのです。
手っ取り早いのが 今の仕事をそのまま有機農業にスライドすることでした。 ただし、ほんとに効率の悪い仕事です。天候にも左右されます。 20年以上経ってもまだまだ試行錯誤の途上です。 少しずつ、少しずつ、前に進んでいこうと思っています。

 作っている作物
作っている作物
お米
- お米は当農場の中心作物。有機JASの認証をうけています。有機JASは農薬・化学肥料を使用しないで3年以上経過した圃場で栽培したもの。1〜2年目は(転換期間中)有機栽培となります。 国の認定を受けた検査機関から認証をうけなければなりません。
いやー、ほんっとに大変。農薬を使わない田んぼの管理も大変だけど、書類の整備や機械の管理まで事細かにチェックされるので、仕事量が倍増します。
- 品種はササニシキ、さわのはな、つや姫の3種。
ササニシキは今主流のもっちりしたお米とは違って、アッサリサッパリした食味が特徴。病害虫に弱く、天候の影響を受けやすいのが玉に瑕で、無農薬で作るのがなかなか大変な品種です。
さわのはなはササニシキ、コシヒカリと同時代に山形県で作られた品種。見た目が悪く時代の波に乗れずに消えていった幻の品種ですが、その美味しさから農家が細々と自家用として繋いできたお米です。 味はもっちり系で、ぬか層や胚芽が固く、玄米や分づき米でも美味しくいただけます。
つや姫は山形県で作られた新しい品種。その名の通りつやがあり、色白ふっくら、きれいな炊き上がり。山形県産は県が種の供給から、収穫後の品質まで管理するプレミアム米。
- 赤米・黒米は有機栽培圃場の一角で作っています。
刈り取り・脱穀は手作業。鎌で刈り取り、天日乾燥、昔懐かしい足踏み脱穀機で脱穀しています。






雑穀
- 雑穀作ってます。ひえ、あわ、きび、たかきび、アマランサス。ゴマも雑穀に入るかな?
その昔水利の乏しいところとか、稲が作れないところは雑穀が作られていました。でも国をあげての米増産が始まるとほとんど消えていきました。 なので、機械化もされていないし、種まきから収穫・脱穀まで作業はほとんど手作業。かなり手間が掛かります。 ましてや無農薬となると・・・。 稲科の作物が多いので、芽が出たばかりの頃は雑草と見分けが付きにくく、除草が大変です。さらに大変なのは収穫時期。スズメたちが大挙してお食事にやって来ます。ちょうど刈り頃の少し前からやって来るので、刈り取り時期を見極めるのが大変。鳥に食べられる前に刈ろうとするとまだ若いし、完熟するのを待っていると、全部食べられちゃうし。 今のところ有効な対策が見つかっていません。トホホ
- 殻付きのものをペット用にも販売しています。小鳥用に「穂」のまま出荷したりしますが、スズメの食害が多いので、なかなかたくさん販売は出来ません。飼い主さんたちにはいつもご不便をおかけしています。
- あと、ポップコーンなんかも作ってます。さすがにこれはスズメには食べられない。フライパンでポンポンやって子供のおやつに出すと、大喜び。









豆
- 豆も農薬・化学肥料は使っていません。 以前は大豆をけっこう作っていました。でも秋は雨が多いこの地方、刈り取りを地域の大豆組合のコンバインに委託したりすると、順番が回ってくる前に雪に降られたり、雨続きでぜんぜん乾燥しなかったりと、なかなか難しいのです。 なので今は自分で刈り取れるくらいの面積しか作っていません。 品種はタチユタカというこの地方で昔から作られている品種です。 家では手作りの味噌や醤油作りに大活躍です。
- 普通の白大豆のほかに黒大豆や青大豆も作っています。 黒大豆は早生の品種で、稲刈りが終わってから刈り取りしようとするともう遅くて、サヤの中で黴びていたりします。なので、ちょうどいいタイミングで刈り取れる品種は無いか、検討中です。 青大豆は〈秘伝〉という品種で、美味しさに定評があります。枝豆で食べてもとても美味しいです。 大粒で刈り取りはちょうど雪が降り始めるあたり。ほかの穀物と刈り取りがかぶらないのがいいところですが、脱穀の機械も全部冬支度で倉庫に片付けて仕舞ったあとなので、ハウスの中で手作業で脱穀です。
- 小豆は赤・黒・白の三品種を少量作っています。なかなかね、需要もないので、趣味の延長みたいな感じです。






野菜
- 野菜はもっぱら地元向けの販売です。地元の直売所やスーパーの地場産野菜のコーナーに置いてもらっています。一つの品目を大量にではなく、少量多品目生産でやってます。
- 冬には2m近く雪の積もる地域なので、冬野菜は作れません。冬をまたぐ野菜も、ラッキョウ、ニンニクはなんとか出来ますが、タマネギはまだ試行錯誤中です。 初夏から晩秋に収穫できる野菜が中心。スナップエンドウに始まって、ズッキーニ、ナス、トマト、キュウリ、枝豆などの夏野菜。ピーマン、ニンジン、大根、コールラビ。果菜、根菜が中心です。 葉菜類やハーブなども作っていますが、まだ出荷には至っていません。
- 栽培するのは固定種の野菜。様々な品種を試して、出来の良かったものから自家採種して、この土地にあったものを増やしていきます。 変わった野菜も試していますが、基本家で料理に使えない(使わない?)ものは消えていってます。 普段の食卓で料理に使えるものが栽培条件です。
- 通販もやってみたいとは思っていますが、冬冬場は出荷できないし、収穫量や種類が時期でまちまちなので、年間を通しての販売は無理かなと思っています。 これからいろいろとやり方を検討していきたいと思っています。









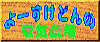 入り口へ
入り口へ
●http://www.denkinojo.com/

![]() 農場のある場所は山形県内陸の北部、山をいくつか越えれば秋田県です。
農場のある場所は山形県内陸の北部、山をいくつか越えれば秋田県です。入り口へ